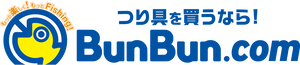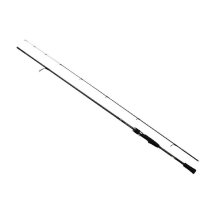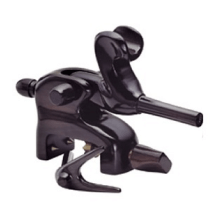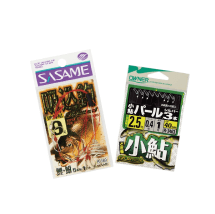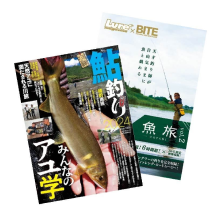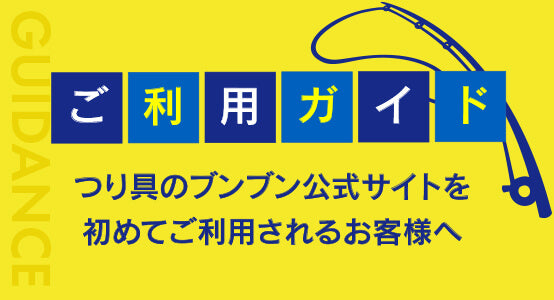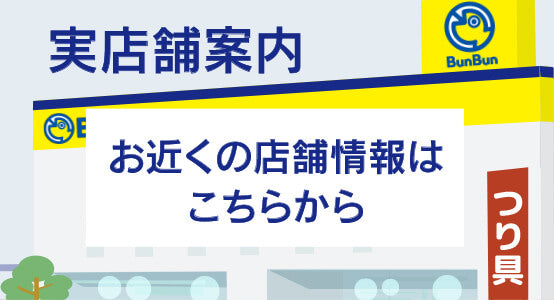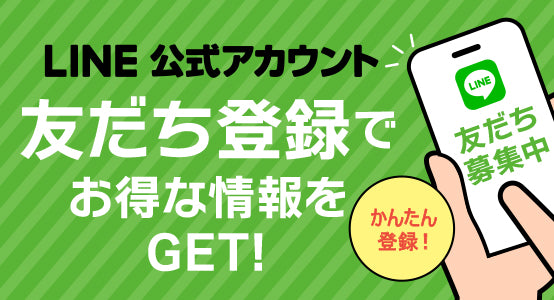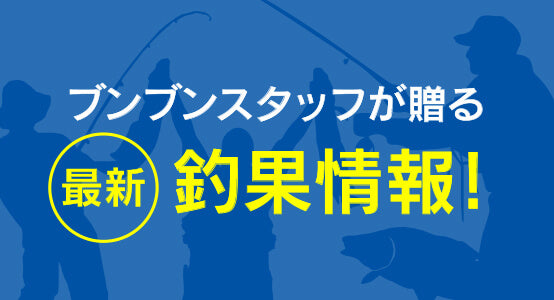船釣りで「もっとテクニカルに楽しみたい」「ゲーム性の高い釣りに挑戦したい」と考えている方に、近年注目を集めているのが船カワハギ釣りです。
繊細なアタリを見極めるスリル、奥深い仕掛けのセッティング、そして釣ったカワハギの絶品の味——一度ハマると抜け出せない魅力が満載です。
しかし、「仕掛けの選び方がわからない」「エサや誘い方に自信がない」といった悩みから、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、船カワハギ釣りに必要な仕掛け選びのポイントや、おすすめの仕掛け、釣果を左右するテクニックまでを徹底解説します。
初心者の方はもちろん、ステップアップを目指す中上級者の方にも役立つ内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
船カワハギ釣りとは?その魅力と基本情報

船カワハギ釣りは、岸釣りとは違い、水深・潮流・底質などの変化が大きい海域で魚を狙うため、より繊細な仕掛け操作や多彩なテクニックが求められる釣りスタイルです。そのため、「食い込み」「アタリの取り方」「仕掛けの動かし方」が釣果を大きく左右します。
魅力としては、まずカワハギならではのアタリの繊細さ。手元に伝わる“じわり”とか“コツン”とか、“違和感”を感じ取る瞬間は、ゲーム性が非常に高く、釣り人を引き込む要素です。
また、仕掛けを微調整していくことで、同じポイントでも潮の上げ下げ・風・水温で反応が変わるため、攻略の幅が広いのも魅力です。
釣った後の味も抜群で、肝の旨味など、食べる楽しみもある魚です。
基本情報として押さえておきたいポイント
- オモリ号数指定のある遊漁船が多いので、出船前に号数を確認しておく。水深・潮流によって必要な重さが変わる。
- 針のタイプ(ハゲ針、丸セイゴ・吸わせ針・早掛け針など)を複数揃えておく。日によって、カワハギの喰い方が変わるため。
- 集寄(スカートやタコベイト・反射板・中オモリ・旗型など)を使うことで視覚・動き・光・音でアピールできるが、過度だと潮を受けて仕掛けが安定しないこともある。
これらを踏まえて、次節では仕掛けが釣果をどう左右するかを見ていきます。
釣果を左右する!船カワハギ仕掛けの重要性

適切な仕掛けを選べるかどうかで、「食い渋り時」に釣れるか、「良型を混ぜられるか」がかなり変わります。仕掛けが合っていなければ、アタリがあっても乗せられない、あるいはアタリそのものを感じ取れない、という結果になりやすいです。
具体的に仕掛けが釣果に影響するポイント
アタリの伝達性(感度)
幹糸・ハリス・針の太さ・素材(フロロカーボン/ナイロン etc.)・接続方式(直結・サルカン・スナップ etc.)などでアタリの伝わり方が変わります。感度を高めると“じれったい食い込み”や“居食い”を逃しにくくなります。
仕掛けの自然な漂い・動き
エサを違和感なく漂わせたり、誘いをかけたときの動きが自然かどうか、集寄や中オモリの有無、針の種類などで調整できます。自然であれば警戒心が強い魚も口を使いやすくなります。
操作性・手返しの速さ
仕掛けを交換したり、エサを付け替えたり、針を変えたりする頻度が多いため、スピーディに行えると、アタリを逃さない機会が増えます。
針の刺さり・強度
カワハギは口が硬く、針先の鋭さが持続するかが重要。針先が鈍っていたり、硬い素材(針の軸の太さ・材質)でないと、掛けてもすっぽ抜けたりバレたりすることがあります。複数替え針を持っておくことをおすすめします。
潮・深さ・潮流等の環境への対応力
仕掛けの全長、ハリスの長さ、オモリの重さ・形、集寄の種類などで、潮流や深さに応じて仕掛けを微調整できるかどうかが釣果に差をつけます。浅場・深場・速い潮・緩い潮でそれぞれベストなセッティングが異なります。
失敗しない!船カワハギ仕掛けの選び方4つのポイント
仕掛けを選ぶ際に特に押さえておきたい4つのポイントを以下にまとめます。
-
針の種類・サイズを状況に応じて使い分ける
- ハゲ針(速掛け・掛かりが速い) vs 吸わせ針・丸セイゴ(食い込み重視)。釣れている魚のサイズや魚の活性でどれが良いか変わります。
- 針の号数も重要。小型中心なら小さい号数、良型狙いであれば大きい号数など太めを検討。硬い口にも刺さる針先の切れ / 鋭さを保つこと。
-
ハリスの長さ・太さ・素材を使い分ける
- 長めのハリス(エダス)を使うと仕掛けが自然に漂うが、感度や操作性が落ちる。短めのハリスは反応が早く取れるが魚に違和感を与えることがある。
- 素材はフロロカーボンが主流。根ズレや擦れに強いため。幹糸に感度の良いPEを使っているものもあります。
-
オモリ(重さ・形・デコレーション)と中オモリの使用
- 重さは遊漁船の指定の号数を確認する。一般的には水深・潮流に応じて20〜40号程度を使うことが多い。浅場なら軽め、深場/潮流速めなら重め。
- 形(六角・丸・カジ型など)によって沈み方・潮切り・沈降時のアピールが変わる。六角タイプは安定性が高い。
- 集寄や中オモリを使うことで、誘い幅・種が増える。ただしアタリがボケることもあるので注意。
-
集寄・視覚・光・動きによるアピール
- タコベイト・ビーズ・反射板・スカートなど、針の近くかオモリ近くに集寄パーツをつけると効果あり。光や動きで魚の好奇心を刺激。
- ただし、集寄が大きすぎたり派手すぎたりすると潮の影響を大きく受けて仕掛けが安定しなくなるため、「アピール」と「自然さ」のバランスを取ること。
状況別おすすめ仕掛けセッティング(浅場・深場・潮流別)
仕掛けは「状況」によって有効な組み合わせが変わります。以下は典型的なケースとそれに適したセッティング例です。
| 状況 | セッティングの特徴 | 推奨ポイント |
|---|---|---|
| 浅場(水深 10〜20m、潮流緩やか) | 軽めのオモリ(20号以下)を使い、ハリスを短め/針サイズ小さめ。集寄は控えめに。針は吸わせタイプや丸セイゴ。 | 自然に漂わせること重視。小型カワハギを確実に取るためのセッティング。 |
| 中深場(20〜40m、水深や潮流中程度) | オモリ号数を20〜30号前後。中オモリや集寄で動きを出す。針は中サイズ(5〜6号)、ハリス長めめも用意。 | 適切な誘いやアピールが効くよう仕掛けに遊びを持たせる。 |
| 深場・潮流が速い/風や波の影響あり | 重めのオモリ(30号+)、オモリ形状は水切れの良い六角やカジ型。ハリスを短めにしてアタリの伝達をよくする。集寄は視覚的なもの(反射板・金/銀針など)を使用。針は太めで硬い口にも対応できるタイプ。 | アタリを逃さないことが第一。強い仕掛けで“掛けた後バラさない”構成を。 |
また、日中・朝夕・潮が動き始めた時など、魚の活性が変化するタイミングでは、仕掛けをこまめに替えて探ることが釣果アップの秘訣です。
自作と市販、どっちが釣れる?それぞれのメリット・デメリット
仕掛けを「買う」か「自作する」か、またはその中間的なカスタムを行うかは、どのような釣りをしたいか、どれだけ手間をかけられるかで判断すべきです。以下にそれぞれのメリット・デメリットを整理します。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 市販仕掛け(完成仕掛け/セット仕掛け) | ・針・ハリス・幹糸・接続具などがバランス良く設計されており、テスト済みであることが多い。 ・手間が少なく即使える。 ・替え針や仕掛けのストックが揃っているタイプが多く、万が一針先が鈍っても交換しやすい。 |
・仕様が標準的なものが多いため、“特殊な条件”に最適というわけではない。 ・針の種類や素材・長さ・号数などの自由度が限られることがある。 ・コストが高くなることも。 |
| 自作/カスタム仕掛け | ・針・ハリス・オモリ・集寄・長さなどを自分好み・その日の状況に応じて作り込める。 ・コストを抑えたり、釣り場での状況に素早く対応できる。 ・釣りの腕・知識が向上する。 |
・製作・微調整に時間がかかる。 ・失敗するとアタリが取れなかったりトラブルが増える。 ・素材や接続具への追加投資が必要。 ・仕掛けの収納・ストック管理が複雑になる。 |
中上級者としては、市販仕掛けをベースに自作パーツ(針・集寄・ハリス等)を組み込んでカスタマイズする方法がバランスが良く、「即戦力」+「自分好みの調整」ができておすすめです。
エサの種類・付け方
エサも釣果に直結する重要な要素です。
あさり(生・むきあさり)
最も一般的なエサ。吸い込み重視の針との相性が良い。むきあさりを使うとアタリが出やすいが、放置すると身が崩れやすいため、使用直前に軽く洗ったり水切りをするのがコツ。
色・匂いの工夫
あさりの色味を変える/おろしニンニク少量つける/塩を振るなど。潮が澄んでいたり水温が低いときは、動きや光・匂いでアピールを足す工夫が効果的。
アサリの付け方
まず、アサリの水管に刺しベロの部分を数回縫い刺しして針先を黒いワタの部分に持ってくるようにします。
青イソメ
手に入りやすい安価な虫エサ。動きと臭いでアピール。アサリとローテーションで使用しエサのアプローチに変化を与える。
青イソメの付け方
青イソメの頭側から通し刺しにする。たらしは長いと端だけちぎって持ってかれやすいので短めで1cmぐらいまでにする。
アタリを逃さない!仕掛けと合わせる誘い方のコツ
仕掛けが良くても誘いがマッチしなければアタリを逃すことが多いです。以下、アタリを取るための誘い方のヒントを挙げます。
ショートピッチ・リフト&フォール
軽めのオモリを使って底を切らない程度にリフト→フォール動作を繰り返す。集寄を軽く揺らすことが魚の食いスイッチを入れることもある。
ゼロテンション釣法
仕掛けを底に着けた後、張らず緩めずラインの張りを保ち、誘い/アタリを待つ。底での“居食い”を取るのに有効。
ワンピッチ誘い・テンポ変化
同じ誘いばかりだと魚が慣れてしまうので、ゆっくり・速く・小刻みに・大きく動かすなどテンポの変化を入れる。
聞き合わせと掛け合わせ
アタリが“モゾモゾ”“じわり”としたものから、“グッ”“コツン”に変化した時を見逃さずに掛け合わせる。魚が吸い込んでいる時を感じ取るためには、針先やハリスなどの感度を高めておくことが前提。
棚の取り方を工夫する
魚が浮いていたり、中層にいて底から少し離れているケースがあるため、オモリを底に着けただけで終わらせず、底から数十cm〜100cmタナを取って探ること。潮の状況・日差し・風などで魚の位置が変わる。